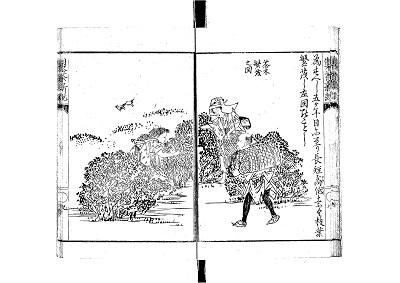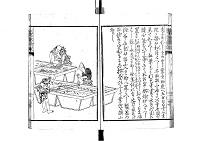2021(令和3)年5月のWeb版貴重書展示 「新茶の季節」
Q617-1『製茶新説』
新茶の季節
私たち静岡県人は、毎日おいしいお茶をいただいていますが、庶民が毎日飲めるようになったのは、実は明治以降であることをご存知でしたか?
お茶は奈良時代から平安時代に中国に留学した僧侶によって日本へ伝わりましたが、当時のお茶は薬用として珍重され、儀式や行事で用いられる程度でした。鎌倉時代、栄西が中国でお茶の効能について感銘を受け、日本に持ち帰り、それまで上流階級に限られていた喫茶の習慣を一般社会に伝えたと言われています。
静岡における茶業の始まりは、鎌倉時代に聖一国師が静岡市の足久保にお茶の種をまいたことがきっかけです。江戸時代後期には、駿河は宇治・信楽と並ぶ煎茶の産地と言われるまでになりました。
明治初期は、世界的な茶の需要もあり、茶は生糸と並ぶ日本の主要輸出品目となりました。清水港は当時、茶の輸出量では日本一でした。
ちなみに、茶の一大優良品種である「やぶきた」は静岡で生まれました。やぶきたを生んだ杉山彦三郎の像や、やぶきたの原樹は当館の近くで見ることができます。
展示期間・場所
期間 5月1日(土曜日)~5月30日(日曜日)
場所 静岡県立中央図書館 閲覧室 貴重書展示コーナー
(期間中、ページを替えて展示します)
展示資料一覧
画像をクリックすると、当館デジタルライブラリーの該当資料が表示されます。